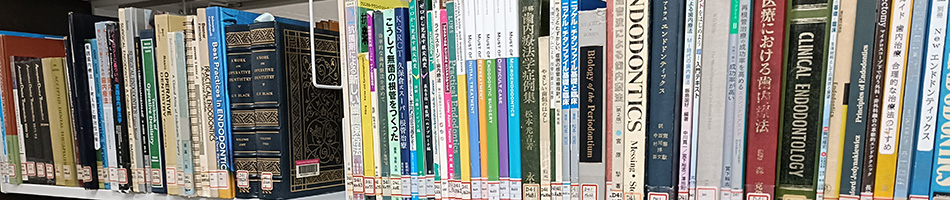大学院に行こう
障害者歯科学講座 野村 宇稔
障害者歯科学講座専修医の野村宇稔と申します。大学院を卒業し,ほぼ研究一色の生活から臨床に出るようになり1年ほどが経ちました。自分の経験を交えて大学院での学びや感じたこと,そしてその後の1年に与えた影響について皆様にお伝えしたいと思います。
私が大学院に進学しようと考えたのは
研修医の時でした。摂食嚥下リハビリテーションを行っている障害者歯科に興味があり大学に残って勉強をしたいと考えていました。大学に残るなら大学院で博士号を取得したほうがいいとの周りからの勧めもあり入学しました。最初は自分のしたい研究は定まっておらず,何をしたらいいかもわからない状態でした。指導してくださる先生や先輩方に教えてもらいながら実験をしていく中で,他の方法で試したらどうなるのだろうかとの思いから関連論文を読み解くうちに徐々に自分の研究していきたいテーマが明確になってきました。それは,研修医時代に興味を持った摂食嚥下機能に関連する誤嚥性肺炎の発症のメカニズムを探求することでした。そこで大学院では,易感染宿主の呼吸器への歯周病原細菌であるFusobacterium nucleatum(F.nucleatum)による影響を検討するために,糖尿病実験モデルを付与した呼吸器由来の細胞や血管内皮細胞にF.nucleatumを接種し,宿主細胞への菌の侵入状況や宿主細胞の炎症応答性を調べることにしました。実験には細菌の取り扱い手法や分子生物学的な実験手法などが必要で有り,細菌学や生化学をはじめ,様々な科の先生方に相談しました。他科であっても親身に相談に乗って頂き,様々な知見を得ることができました。論文を書く上で必要な結果を想定しながらの実験計画の立案はもとより,実際の実験手技手法には,過去の論文を参考に自分自身が考える必要がありました。想定した結果が得られないことも多く,様々な可能性を模索しなければなりませんでした。しかしながら,試行錯誤をして結果を導き出し,4年間で論文をまとめる経験は大学院でなければ得られないと思います。この経験が今では問題解決能力の一端となり,臨床の場面で患者さんのご家族や施設の職員さんとのコミュニケーションの基盤として活かされていると強く実感しています。大学院では,実験,発表資料の作成,参考文献の検索など短い4年間でやることが多く,スケジュール管理をしっかりと行う必要があり,大変ではありましたがその経験もまた自分のキャパシティーを広げることにつながりました。卒後の大切な時間,大学院で4年間学ぶというのは開業医で働いている同級生から歯科医師として技術面で後れを取ってしまっているのではないか?開業医で技術を磨いた方がいいのではないかと思うこともあるかと思いますが,1年が経った今,4年間の差はそれほどないように感じています。皆さんも周りに置いていかれると心配はせずに大学院で知識を深めてから臨床を学ぶというはどうでしょうか?大学院での経験はかけがえのないものだと思います。この話が大学院に行くか悩んでいる方の助けになると幸いです。