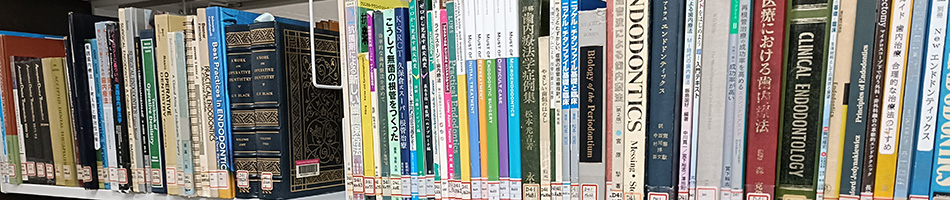大学院へ行こう
歯科矯正学講座 宮崎樹梨
拙い文章ですが,大学院への進学を検討している皆さんの参考になれば幸いです。
私は,父が大学院に進学していたこともあり,自分自身も大学院への進学を考えていました。父の仕事に同行して,子供のころから海外学会に参加していたので発表をする先生たちを見て,自分もいつかはという気持ちで進路を考えていました。しかし,どこの大学院に行って何を研究するのかについては深く考えていませんでした。6年生のころから矯正科に興味を持ち,母校の先輩が数人松戸歯学部の矯正科に入局していたので知り合いがいるという安心感もあり私自身も入局を希望するようになりました。説明会に行き,当講座では近くの小学校で毎年研究データを採得し,そのデータを資料として用いて歯列と口腔機能との関連性を調べる研究をしている話を聞き興味を持ち,入局と大学院の進学を決めました。
医局内に大学の先輩はいましたが,他大学出身だったので他科に知り合いの先生もいなくて馴染めるのか,研究を4年間続けられるのか不安なまま新年度を迎えました。ちょうど入学したときは新型コロナの感染拡大により緊急事態宣言が出ており,出勤の日数が減ったり授業がオンラインになったりとイレギュラーなことが多かったですが,ゆっくりしたペースで医局に馴染めて研究のテーマを考える時間もあったので私には合っていたのかなと思います。医局の先輩も研究の相談に乗ってくれたり他科の先生と共同で研究したりと,他大学出身の私にも親身になってくれて研究に励むことができました。
大学院での生活は,基本的には医局員と変わらないですが臨床や実習の合間に研究を進めていくので慣れるまではペースを掴むのが大変でした。矯正科では,新人研修として講義があったり,ワイヤーを曲げたり,診療のアシストについたり,患者さんの分析があったり大学にいる間は忙しかったので合間や診療時間が終わった後に研究をしていました。大学院の先輩や同期達と医局で研究について話し合って過ごした時間は大切な思い出です。大学院時代は,初めてのことばかりでわからないことやうまくいかないこともたくさんありましたが,初めてポスターを作ったときや論文を投稿したときはとても達成感がありましたし,研究者としてのスタートラインに立てた気持ちでした。
私が大学院の時に行っていた研究は,上顎小臼歯の三次元的形態についてという内容です。本来やろうと思っていた研究の内容とは少し違う方向になりましたが,教授と指導してくださった先生たちのおかげで無事学位を取得することができました。大学院の1,2年生の時は新型コロナの感染拡大により,学会が中止になったりオンラインでの開催になったりしたので,私が実際に学会会場でポスター発表ができたのは3年生の秋頃でした。学会会場での発表は1回だけでしたが,データの処理やポスターの準備など初めてのことばかりで大変でしたけどとてもいい経験ができたと思っています。新型コロナによりタイミングが合わず,叶いませんでしたが大学院生の時に海外学会でのポスターや口頭での発表も経験してみたかったです。
大学院での生活を振り返ると,いいデータが出なかったり研究のテーマが変わったりとうまくいくことばかりではありませんでした。研究だけでなく,日々の臨床や分析,技工物作成など色々なタスクに追われて忙しい毎日でしたが,自分自身を大きく成長させてくれた4年間でした。教授をはじめとした研究を指導してくださった先生や医局の先生方や進学を後押ししてくれた家族に支えられて乗り越えられたと思っています。進路決定は悩むところだと思いますが,4年間はあっという間ですし,大学院に進学しなかったら出来なかった経験がたくさんできるので,少しでも興味があったら是非大学院に進学していただきたいです。